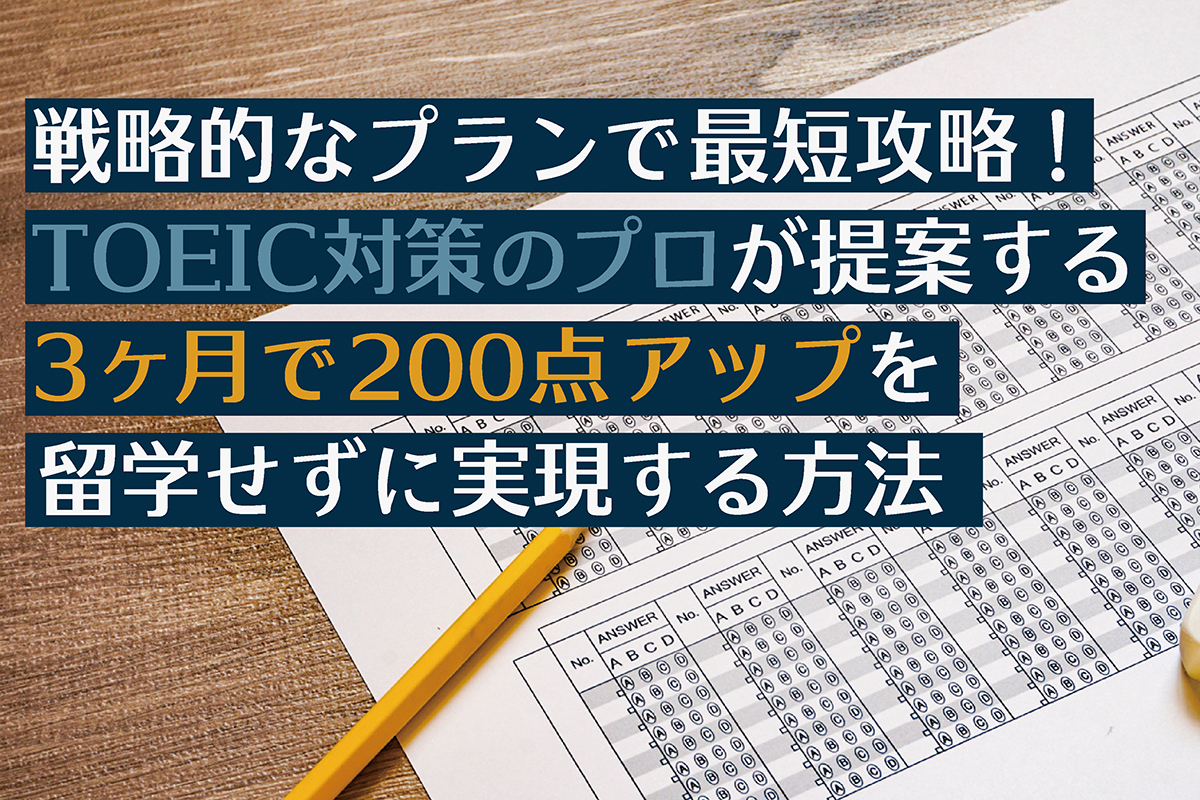社内公用語が英語の企業一覧|メリット・デメリットも徹底解説
楽天やユニクロといった有名企業が社内公用語を英語に切り替えるなど、ビジネスの世界で英語の重要性はますます高まっています。
グローバル化が進むなか、「英語が公用語の企業で働いてみたい」「どんな準備が必要なんだろう?」と気になっている方もいるかもしれません。
この記事では、なぜ社内公用語を英語にする企業が増えているのか、その理由から具体的な企業一覧、そして企業と社員それぞれにとってのメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。
Contents
なぜ社内公用語を英語にする企業が増えているのか

最近、社内公用語を英語にする日本企業が増えています。これは単なる流行ではなく、企業がグローバル市場で生き残るための、はっきりとした考えに基づいた動きです。
主な理由として、以下の3つのポイントが挙げられます。
- 世界を相手にビジネスをするための競争力を高めるため
- 国内外から優秀な人材を集めるため
- 社内のコミュニケーションをスムーズにするため
これらは、変化の激しい今のビジネス環境で、企業が成長を続けるためにとても大切なことです。ここからは、それぞれの理由について具体的に見ていきましょう。
1. 世界を相手にビジネスをするための競争力を高めるため
海外とのビジネスでは、言葉の壁が原因で商談がスムーズに進まなかったり、契約に時間がかかったりすることがあります。社内の公用語が英語であれば、こうした問題を減らし、海外企業とのやり取りを円滑に進めることができます。
また、最新の技術や市場のトレンドに関する情報は、多くの場合まず英語で発信されます。英語を日常的に使う環境を整えることで、こうした有益な情報をいち早くキャッチし、ライバル企業より一歩先に進むための判断ができるようになります。
2. 国内外から優秀な人材を集めるため
少子高齢化が進む日本では、国内だけで優秀な人材を確保し続けるのが難しくなってきています。そこで多くの企業は、世界に目を向けて人材を探し始めています。
社内公用語を英語にすることで、日本語が話せないという理由だけで採用できなかった優秀な人材を、世界中から迎え入れることが可能になります。多様なスキルや文化を持つ人々が集まることは、新しいアイデアやサービスを生み出すきっかけにもつながります。
3. 社内のコミュニケーションをスムーズにするため
多国籍の社員が働く環境では、特定の言語を話すグループだけで大切な情報が共有されてしまう、といった問題が起こりがちです。これでは、チームとしての一体感が生まれにくくなってしまいます。
コミュニケーションを英語に統一することで、社員全員が同じ情報にアクセスできるようになります。これにより、情報格差がなくなり、会社全体でスムーズな意思疎通が可能になるため、より良い協力体制を築くことができます。
社内公用語を英語にしている日本企業一覧

実際にどんな企業が社内公用語の英語化に取り組んでいるのでしょうか。ここでは、代表的な企業とその取り組み状況を表にまとめました。
会社全体で一斉に導入しているケースや、特定の部署から少しずつ始めているケースなど、その進め方は会社によってさまざまです。
| 企業名 | 取り組み状況 |
| 楽天グループ株式会社 | 2012年から全社的に英語を公用語化 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 本社部門や主要な会議では英語を使用。段階的に拡大中 |
| 株式会社資生堂 | 2018年からグローバル本社機能を持つ部門で英語を公用語化 |
| シャープ株式会社 | 2016年の鴻海グループ傘下入りに伴い、英語化を推進 |
| 本田技研工業株式会社 | 2020年を目標に、グローバル会議での英語公用語化を推進 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | グローバルな経営情報や主要会議は原則英語を使用 |
| 武田薬品工業株式会社 | 2013年以降、研究開発や海外事業部門を中心に英語化 |
| 株式会社LIXIL | 経営層の会議やグローバルなコミュニケーションは英語を使用 |
※各社の取り組み状況は変更されている可能性があります。
<参考>
・Rakuten Driven by Innovation Integrated Report 2024(PDF)
・Human Resources | ANNUAL REPORT 2018 | Shiseido group website
・Honda-SR-2016-en-062(PDF)
【事例】楽天グループの英語公用語化と10年の歩み

社内公用語の英語化を語る上でとても参考になるのが、いち早くこの取り組みを始めた楽天グループの事例です。
ここでは、楽天が英語公用語化(Englishnization:イングリッシュナイゼーション)を宣言してから10年以上が経った今、どんな目的で始め、どのように進めてきたのか、そして現在どうなっているのかを具体的に見ていきます。
導入の背景|楽天が英語公用語化に踏み切った理由
楽天が英語公用語化を宣言したのは2010年でした。一番の目的は、創業者である三木谷浩史社長が掲げた「グローバルで通用する新しいことを生み出す会社になる」という目標を達成するためです。
世界中の市場でサービスを展開し、さまざまな国から優秀な人材を集めるには、世界共通語である英語が必要だと考えたのです。これは、日本の会社「楽天」から世界の「Rakuten」へとステップアップするための、大きな決断だったと言えるでしょう。
実施の過程|TOEIC800点目標が与えた影響
楽天は、約2年間を準備期間として英語化を進めました。特に大きな影響を与えたのが、TOEICのスコアを昇進や昇格の条件の一つにしたことです。
宣言した当初、全社員の平均スコアは526点でしたが、会社はeラーニングや社内講座といった学習の機会をたくさん用意して、社員の勉強を後押ししました。
社員一人ひとりが努力した結果、平均スコアは800点を超えるまでに大きくアップしました。具体的な数値目標があったからこそ、会社全体の英語力が上がった良い例です。
現在の姿|導入10年以上で見えた成果と課題
英語公用語化から10年以上が経ち、楽天では大きな成果が出ています。特に、東京本社のエンジニアの約8割が外国籍社員になるなど、いろいろな国籍の社員が集まるようになりました。
グローバルな人材が集まることで、新しい技術やアイデアが生まれやすくなったと言われています。また、海外の会社を買収する際にも、英語でのスムーズなやり取りが役立ったと考えられています。
その一方で、「あうんの呼吸」のような、日本語ならではの細かいニュアンスで伝わっていた会社の文化を、英語でどう伝えていくかといった新しい課題も出てきています。
<参考文献>
・Englishnization: A personal journey
・Englishnization: Embracing a global vision through language
・第45回 社内公用英語化の宣言から12年目。 楽天グループの現在地から改めて学ぶこと
【企業視点】社内公用語を英語化するメリット・デメリット

ここからは企業の立場に立って、社内の公用語を英語にしたときのメリットとデメリットを見ていきましょう。
英語化はグローバルで戦える力をつけるうえで意味のある取り組みですが、実際に導入するにはしっかりした計画と準備が必要です。
こうしたポイントを理解しておくことで、企業がなぜ英語化に踏み切るのか、そしてどんな課題を想定しているのかがわかります。
メリット1. 海外展開を加速し競争力を強化できる
社内の共通言語を英語にすると、海外企業とのやり取りがスムーズになります。言葉の壁による誤解や時間のロスが減るので、仕事全体のスピードが上がり、取引や契約も進めやすくなります。その分、海外展開のチャンスを広げやすくなるのもメリットです。
さらに、世界の市場動向や新しい技術の情報を社内で共有しやすくなります。翻訳を待つ手間がなくなるため、すぐに戦略に取り入れることができます。こうした積み重ねによって、国際的な競争にも対応しやすくなり、企業の力を強めることにつながります。
メリット2. 優秀な人材を採用・定着しやすくなる
社内の公用語を英語にすると、採用の対象を世界中に広げられるようになります。これにより、国籍に関係なく高いスキルや経験を持つ人材を採用できるチャンスが増えます。国内だけでは出会えない優秀な人材とつながれるのは大きな強みです。
また、多様な文化や価値観を持つ人材が集まることで、組織に活気が生まれ、今までになかったアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。外国人社員にとっても働きやすい環境になるため、定着率が高まりやすいのもメリットです。
メリット3. 情報共有が速まり意思決定が早くなる
言語の壁がなくなると、国や部門を越えた情報共有がスムーズになります。全員が同じ言語で議論できるようになるため、認識のズレが減り、自然と一体感も強まります。
その結果、経営陣は会社の状況を正確に把握しやすくなり、ビジネスチャンスを逃さない迅速な意思決定につながります。ただし、社員ごとの英語力に差がある場合は、逆にコミュニケーションが滞ることもあるため注意が必要です。
メリット4. 国際的な信頼性を高められる
社内公用語を英語にすることは、グローバル市場でビジネスをしていくという会社の強い決意表明になります。これは、変化の激しい世界経済の中で、積極的に挑戦し続ける姿勢を会社の外に示すことにもつながります。
海外の取引先や投資家は、言葉の壁を乗り越えようとする会社を高く評価する傾向があります。世界で通用する先進的な会社だと見なされ、会社全体のイメージアップや信頼感の向上といった良い影響が期待できます。
デメリット1. 研修やサポートにコストがかかる
社員の英語力を一定のレベルまで引き上げるためには、それなりのお金がかかります。外部の英語研修サービスを頼む費用はもちろん、eラーニング教材の購入費や利用料も継続的に必要になります。
また、勉強をサポートする専門の部署を作る場合には、そこに所属する社員の人件費も考えなくてはなりません。英語化は、効果が見えるまでに時間がかかる長期的な投資だと考えておくことが大切です。
デメリット2. 導入初期は業務効率が下がる可能性がある
特に英語化を始めたばかりの頃は、多くの社員が慣れない英語でのやり取りに戸惑うことが考えられます。会議では言いたいことがうまく伝わらなかったり、メールを作るのに今までより時間がかかったりする場面が増えるでしょう。
こうした状況は、一時的に会社全体の仕事の効率を下げてしまう可能性があります。細かいニュアンスの誤解から仕事のやり直しが発生するなど、スムーズな業務の妨げになるかもしれない、と覚えておくのが良いでしょう。
デメリット3. 英語力の差が不公平感や離職につながる
社員の間にもともとある英語力の差が、仕事の分担や評価に直接影響してしまうことがあります。例えば、英語が得意な社員に海外とのやり取りといった大事な仕事が集中して、負担が大きくなりすぎるかもしれません。
一方で、英語が苦手な社員は、大事な情報から取り残されていると感じたり、正当に評価されていないと感じたりして、不満を抱くことも考えられます。このような状況は社員のやる気を下げ、最悪の場合、優秀な社員が会社を辞めてしまうことにもなりかねません。
【社員側】社内公用語を英語化するメリット・デメリット

次に、働く社員の立場から、社内公用語が英語であることのメリットとデメリットを見ていきましょう。自分のキャリアにとって大きなチャンスになる一方で、それなりの努力も必要になります。
メリット1. 世界を舞台にした仕事に挑戦でき、キャリアアップにつながる
日常的に英語を使う環境にいると、海外勤務や国を越えた大きなプロジェクトに参加するチャンスが増えます。英語を使った仕事の経験は、自分の市場価値を高める上で大きな武器になるでしょう。
将来的には海外の会社に転職したり、外資系の会社でより責任のある立場を目指したりするなど、キャリアの幅が大きく広がります。日本にいながら、世界レベルのキャリアを築いていくことが可能になるのです。
メリット2. 仕事を通して実践的な英語力が伸びる
英語の勉強で多くの人がつまずくのが、「習った英語を実際に使う機会がない」という点です。せっかく覚えた単語やフレーズも、使わなければすぐに忘れてしまいます。
その点、社内公用語が英語なら、会議やメール、プレゼンなど、毎日の仕事そのものが英語を練習する絶好のチャンスになります。机の上での勉強だけでは身につかない、本当に「使える」ビジネス英語が自然と伸びていきます。
メリット3. 海外出張や駐在など新しいチャンスが広がる
英語でスムーズにやり取りできる力は、海外出張や駐在員に選ばれるための前提条件になることがほとんどです。英語が使えることで、海外で働くという選択肢が、より現実的なものになります。
会社が海外にビジネスを広げていく中で、自分がその中心メンバーとして活躍できるチャンスも増えるでしょう。これは、仕事の幅を広げるだけでなく、自分の人生の可能性を広げるきっかけにもなります。
デメリット1. 勉強に時間と労力がかかる
今の英語力に自信がない場合、仕事についていくために勤務時間外での勉強が必要になります。日々の仕事で疲れている中で、さらにプライベートの時間を使って勉強を続けるのは、決して簡単なことではありません。
新しい単語を覚えたり、会議で話す内容を事前に練習したりと、常に努力が求められます。英語力を保ち、さらに伸ばしていくためには、強い意志と自分で時間を管理する力が必要です。
デメリット2. 誤解やコミュニケーションでのストレスが増える
言葉が変わると、これまで当たり前に伝わっていた細かいニュアンスや気持ちがうまく伝わらない、というもどかしさが生まれます。常に頭の中で日本語と英語を変換しながら話すことによる精神的な疲れも、多くの人が感じるストレスです。
「文法が間違っていたらどうしよう」「変な意味に取られたらどうしよう」といったプレッシャーを感じて、本来の実力を発揮できなかったり、発言をためらってしまったりすることもあります。
デメリット3. 英語が苦手な社員が不安や孤立を感じやすい
英語の会議の内容が理解できなかったり、同僚たちの英語での雑談の輪に入れなかったりして、職場で孤立感を深めてしまうことがあります。自分だけが取り残されているような感覚は、大きな不安につながります。
英語ができないことへの焦りや劣等感が、精神的な負担になることも少なくありません。こうした状況が続くと、仕事へのやる気が下がり、最悪の場合、会社に居づらくなって辞めてしまう、というケースも考えられます。
社内公用語を英語化している企業で働く・転職するために必要な英語力

「英語が公用語の企業で働きたいけれど、どのくらいの英語力が必要なんだろう?」と不安に思う方もいるでしょう。
ここでは、求められる英語力の目安について解説します。
1. TOEIC700点以上がひとつの目安。仕事によっては800点以上も
一般的に、多くの会社で一つの基準にされているのがTOEICのスコアです。例えば、「ユニクロ」などを運営するファーストリテイリングの求人では、応募の条件としてTOEIC700点以上を目安にしている例が多く見られます。
ただし、これはあくまで仕事をする上での最低ラインと考えた方が良いでしょう。海外営業や管理職など、英語で難しい交渉や議論をする仕事では、800点以上、あるいはそれ以上の実践的な会話力が求められることも珍しくありません。
2. 今の英語力以上に「学び続ける姿勢」が大切
もちろん、応募した時点での英語力が高い方が有利なのは確かです。しかし、それ以上に多くの会社が大切にしているのが、入社してからも勉強を続け、成長しようとするやる気です。
面接などでは、現在のスコアだけでなく、これまでどんな風に英語を勉強してきたか、そして入社後に会社のサポートなどを利用してどう追いついていきたいかを具体的に話すことが大切です。
「今の英語力に満足せず、これからも学び続けます」という前向きな姿勢を見せることが、自分の可能性を信じてもらうためのポイントになります。
本気でビジネス英語を学ぶなら英語コーチング「イングリード」

ここまで読んで、「自分にはちょっと難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。特に、社員側のデメリットで挙げた「勉強時間の確保」や「コミュニケーションのストレス」といった問題を一人で乗り越えるのは、なかなか大変です。
そんな悩みを解決する方法として、私たち英語コーチングサービス「イングリード」がお手伝いできます。
ただ英会話レッスンをするのではなく、科学的な根拠と専門コーチのサポートで、英語学習をゴールまで導きます。
第二言語習得論(SLA)という、言葉を効率よく身につけるための科学的な理論に基づいて、一人ひとりに合った学習プランを作成します。さらに、採用率0.3%という厳しい基準をクリアした優秀な日本人コーチが、毎日の勉強の進み具合からモチベーションの維持まで、マンツーマンでしっかり支えます。
「仕事で本当に使える英語力を身につけたい」「今度こそ挫折したくない」「短期間で英語力を伸ばしたい」と考えている方に、イングリードの英語コーチングはおすすめです。
【事例紹介】イングリードで英語力を伸ばした利用者の声

実際にイングリードを利用して、仕事で求められる英語力を手に入れた方々のリアルな声を紹介します。
具体的な成果を見ることで、ご自身の成功をイメージしやすくなるかもしれません。
1. 3ヶ月でTOEIC315点アップしたサチコさん
ホスピタリティー業界で働くサチコさんは、会社の昇進条件であるTOEIC730点のクリアと、増えている外国人のお客様への対応に課題を感じていました。
イングリードで学習を始めてわずか3ヶ月で、TOEICスコアが440点から755点へと315点もアップしました。苦手だったリスニング力が上がり、ビジネスで使われる単語も正確に聞き取れるようになったそうです。
今後は、お客様に最高のおもてなしをするため、さらに高いレベルを目指して勉強を続けています。
2. VERSANTスコア29点アップで海外出張に挑戦した浅野義人さん
輸送用機器メーカーに勤める浅野さんは、海外拠点とのメールや会議が増える中で、ご自身の英語力に強い危機感を持っていました。
3ヶ月のコーチングの結果、スピーキング力を測るVERSANTスコアが12点から41点へと大幅にアップしました。
英語を話すことへの苦手意識がなくなり、勉強そのものが習慣になったといいます。近々予定されている海外出張で、身につけた英語力を活かして、より実践的な会話を成功させたいと意気込んでいます。
3. 海外展開を見据えてビジネス英語を学び直した藤保修一さん
会社を経営する藤保さんは、今後の事業拡大のためには海外展開が必要と考え、ビジネスで通用する本物の英語力を身につけるために受講を決めました。
8ヶ月間の学習を経て、VERSANTスコアが34点から51点にアップしました。独学では気づけなかった自分の弱点を基礎からやり直し、自信を持って仕事で使える英語力を取り戻せたと実感されています。
今後の目標は、自社の素晴らしいビジネスを、ご自身の言葉で海外に広げていくことです。
社内公用語の英語化に関するよくある質問
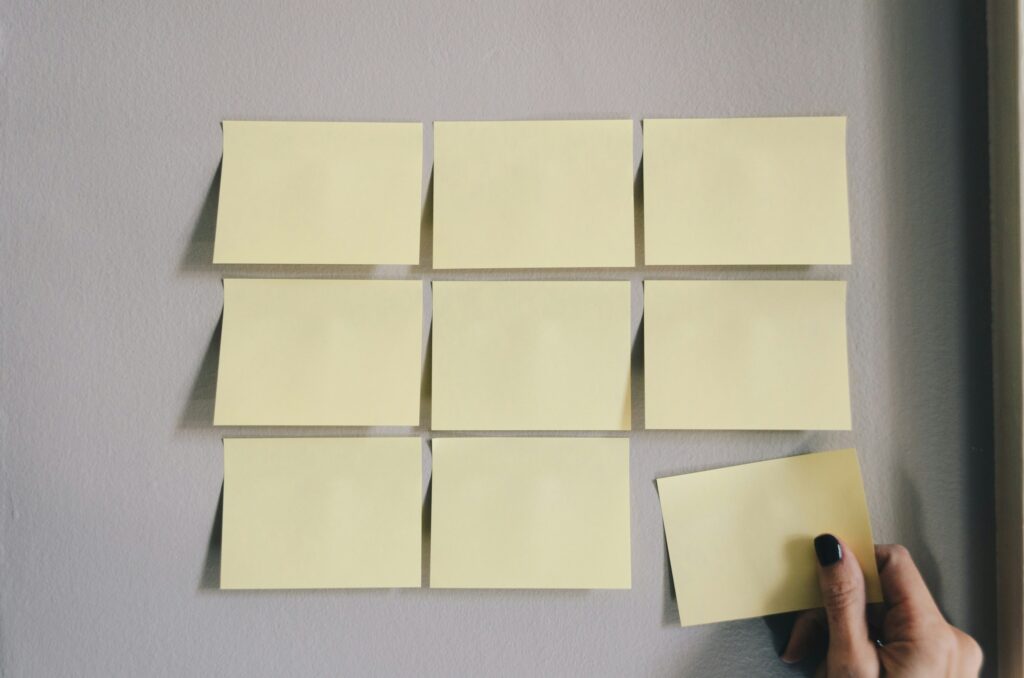
最後に、社内公用語の英語化についてよくある疑問を解消し、次のステップに進みましょう。
Q1. 英語がほとんど話せなくても、入社後についていける?
A. ご本人のやる気と、会社のサポート体制がとても大切になります。 実際、入社した時は英語力が高くなくても、その後の集中した勉強で追いつき、第一線で活躍している人はたくさんいます。
大切なのは、学びたいという気持ちと、それを続ける力です。一人での勉強が不安な場合は、イングリードのようなコーチングサービスを利用して、専門家と一緒に二人三脚で勉強を進めるという道もあります。
Q2. 外資系企業で英語を使うのと何が違う?
A. 外資系企業は、もともと英語でコミュニケーションを取る文化が当たり前になっています。一方、日本の会社が英語を公用語にする場合は、長年慣れ親しんだ日本語中心の文化から英語中心の文化へ変えていく、という点に大きな違いがあります。
そのため、社員が変化に戸惑わないようにケアしたり、日本的な考え方をどう英語で伝えるかを考えたりと、日本の会社ならではの工夫が必要になることがあります。
Q3. 翻訳ツールは仕事でどこまで使える?
A. 会社の方針や会議の内容にもよりますが、うまく使い分けるのが現実的です。 メールの下書きやチャット、資料作成の補助などでは、翻訳ツールがかなり役立ちます。
しかし、リアルタイムでの大事な話し合いでは、文脈を読み間違えたり、細かいニュアンスが伝わらなかったりする限界もあります。特に会社の機密情報や契約に関する内容など、間違いが許されない場面では、AI翻訳の結果を必ず人間がチェックするなど、慎重に使うことが求められます。
社内公用語の英語化は、会社と社員が共に成長するチャンス

社内公用語の英語化は、慣れるまでは大変なこともあるでしょう。しかし、これを乗り越えた先には、会社にとっては世界市場での大きな成長が、社員にとってはキャリアの可能性を大きく広げるチャンスが待っています。
今回紹介したメリット・デメリットや必要なスキルを参考にして、ご自身にとって英語化がどんな意味を持つのかを考えてみてください。英語というツールを手に入れることは、これからの時代を生き抜くための力になります。
「自分の英語力をもう一段階レベルアップさせたい」「世界を舞台に活躍したい」と本気で考えている方は、まずはプロの力を借りて、効率的に勉強を始めてみてはいかがでしょうか。
イングリードでは、目標や課題に合わせた学習プランを提案する無料カウンセリングを行っています。少しでも気になった方は、ぜひお気軽にご相談ください。